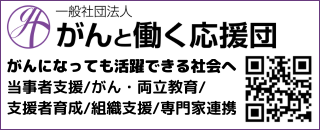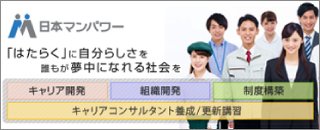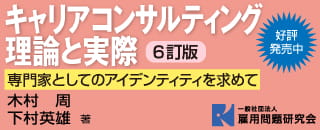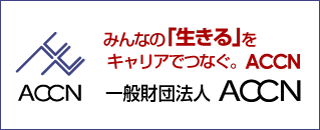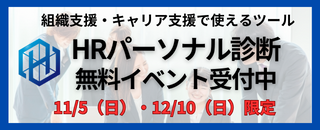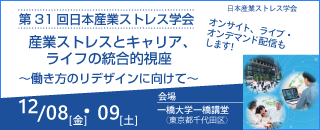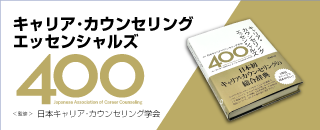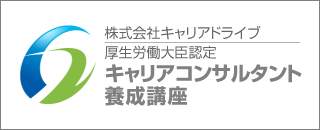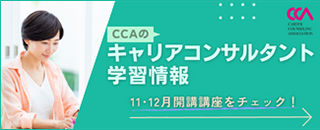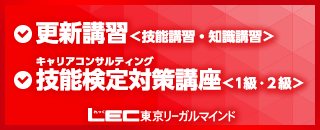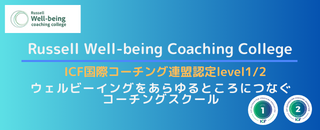発達障害のある大学生の理解と支援(仮)
発達障害のある大学生に効果的なキャリア支援が行えるよう、発達障害についての理解を深め、それをふまえた効果的な関わり方や、支援におけるポイントをお話しします。まずは、発達障害の概要について、そして診断はないが発達障害の傾向がうかがえる学生の特徴などを説明します。それらをふまえて、そういった学生達と関わる際の留意点をご紹介します。また、キャリア選択においては、障害の有無にかかわらず自己理解が重要になります。自己理解が進むことで、必要な支援や配慮を求めるセルフ・アドボカシーも可能になります。心理検査の活用など、自己理解を進めるための方法についてもお話しします。
講師

高橋 知音(たかはし・ともね)
信州大学 学術研究院(教育学系)教授。University of Georgia, Graduate School of Education修了(Ph.D.)。信州大学講師、助教授、准教授を経て2010年から現職。大学では教員養成、心理師養成に加え、障害学生支援の発達障害関連の専門委員も担当。専門は臨床心理学、教育心理学。公認心理師、臨床心理士、特別支援教育士SV。日本LD学会副理事長、全国高等教育障害学生支援協議会理事、文部科学省障害のある学生の修学支援に関する検討会委員、日本学生支援機構 障害学生修学支援実態調査/分析協力者会議委員などを務める。務める。主な著書に『読み書き困難の支援につなげる 大学生の読字・書字アセスメント』(金子書房)、『発達障害の大学生のためのキャンパスライフQ&A』(弘文堂)、『発達障害のある大学生の支援』(金子書房)、『発達障害のある人の大学進学 : どう選ぶかどう支えるか』(金子書房)などがある。
ナラティヴ・カウンセリングのデモセッション
対人支援の場においては、さまざまな研修の機会がありますが、カウンセリングの実際のやりとりを見る機会はあまりありません。今回は、本研修会の参加者の中から1名有志を募り、クライアント役になってもらい、デモセッションをします。クライアント役は何らかの役に就くのではなく、ご自身の話をしてもらいます。
カウンセラー役は、ナラティヴ・セラピーを専門にしていますので、この影響を多分に受けたものとはなりますが、ナラティヴ・セラピーの技法を見せるためのデモンストレーションではありません。ナラティヴ・セラピーの姿勢を維持しながら、相手の語りに寄り添っていきたいと考えています。
本研修では、個人的なことが話されます。参加にあたっては、個人的なことを絶対に外に持ち出さないことが求められます。
講師

国重 浩一(くにしげ・こういち)
1964年、東京都墨田区生まれ。ニュージーランド、ワイカト大学カウンセリング大学院修了。臨床心理士、ニュージーランド、カウンセラー協会員。鹿児島県スクールカウンセラー、東日本大震災時の宮城県緊急派遣力ウンセラーなどを経て、2013年からニュージーランドに在住。同年に移民や難民に対する心理援助を提供するための現地NPO法人ダイバーシティ・カウンセリング・ニュージーランドを立ち上げる。2019年には東京に一般社団法人ナラティヴ実践協働研究センターの立ち上げに参加。著書に、『ナラティヴ・セラピーの会話術』、『震災被災地で心理援助職に何ができるのか?』、『どもる子どもとの対話』など。訳書に、『ナラティヴ・アプローチの理論から実践まで』、『ナラティヴ・メデイエーション』、『心理援助職のためのスーパービジョン』『カップル・カウンセリング入門』など。
私の人生経験から学んだこと ―弱さの受容とそこから生まれてくる強さ―
大学時代(1954年)から現在まで70年にわたる私の人生経験、臨床経験、教師経験から多くのことを学んで来ています。キャリアも哲学者志向から、臨床心理実践家志向、それに伴う仕事先、就職先の選択など様々な体験を重ねて、今日に到っています。
今回の講演では、自分自身を振り返えると「弱さの受容と生まれてくる強さ」「コミュニティネットワークの創設と仲間たちとの相互理解、相互支援の中で生きて、生かされてきたイメージ」が強く浮かんできています。
皆さんがそれぞれ、ご自分の人生の専門家として歩まれるプロセスに何らかの参考になればとても嬉しいです。
参考:村山正治著『私のカウンセラー修業』(2022 誠信書房)
講師

村山 正治(むらやま・しょうじ )
京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了 教育学博士 九州大学名誉教授
PCA、エンカウンター・グループ、ピカジップ、フォーカシングが専門です。
ロジャース研究所(CSP)に留学、ジェンドリンを日本に招待など日本に於けるPCAとフォーカシングの発展に貢献しています。日本心理臨床学会賞、日本人間性心理学会賞を受賞しています。
個と組織をつなぐ場の設計と運用~組織開発の視点から~
講師

土屋 耕治 (つちや・こうじ)
南山大学人文学部心理人間学科准教授
1982年、神奈川県横浜市生まれ。2011年3月名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士後期課程単位取得退学。南山大学講師を経て、2021年4月より現職。専門領域は、社会心理学、組織開発、体験学習。米国NTL Institute OD Certificate Program修了。公認心理師。
社会心理学の実証的研究に加え、Tグループのトレーナー、組織開発のコンサルティングも行うほか、OD Network Japanの基礎講座の講師も担当している。
組織開発では、事例の心理学的理解、倫理、思想史、熟達化を専門としている。
主な論文として、『組織開発 (OD) の倫理: 日本における現状の理解と今後の展開へ向けて』(組織開発研究、2020)、『組織の「時間」への働きかけ: 組織開発における組織診断の事例から』(実験社会心理学研究、2016)など。
キャリアコンサルタントである精神科医が語る「キャリアとメンタルの統合支援」とは ~今後求められる、企業人事スタッフと精神科医(産業医)の連携強化のために~
企業においては、コロナへの対応や働き方の多様化への対応が求められている中、メンタル面での不調を訴える従業員が増加している状況に直面しています。そして、不調を訴える本人も、また所属先の企業人事部もその対応に苦慮している中、クリニックを開業する精神科医であり、企業の産業医であり、そしてキャリアコンサルタントでもある小川耕平先生が、企業人事スタッフの方々、企業領域での活動に携わるキャリアコンサルタントの皆さんへ日頃の実務経験で蓄積されてきた貴重な情報や対応へのヒントをお話し頂きます。また、小川先生のクリニックでカウンセラリング業務を担当する野条美貴氏(当学会理事)にキャリアとメンタルの統合支援について現場視点でお話し頂きます。
講師

小川 耕平(おがわ・こうへい)
目黒駅前メンタルクリニック 院長
専修大学・同大学院 兼任講師、青山学院大学 非常勤講師
精神科医、産業医、博士(医学)、国家資格キャリアコンサルタント
福島県立医科大学卒業、日本医科大学大学院修了
専門:精神薬理学・司法精神医学・産業精神保健学
大学病院勤務、市中病院での精神科救急医療従事を経て、平成30年から現職。医療機関で医療従事者とキャリアコンサルタントの協働での復職支援・就労支援のプログラムを体系的に始めるなど、働く人のメンタルヘルスや障がい者雇用に関する様々な社会的課題の解決を目指した多面的な多職種連携によるアプローチを実践するほか、産業医や司法精神医学の活動も行っている。
- 研修会参加にあたっての、事前の申込や連絡は必要ありません。
- 研修会は、大会(帝京平成大学)で開催し、その様子をzoomでリアルタイムに視聴をすることが可能です。大会終了後は、オンデマンド形式で視聴ができます。視聴期間は、約1か月を予定しています。